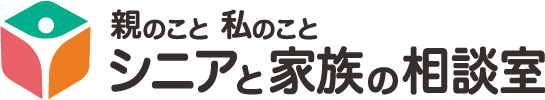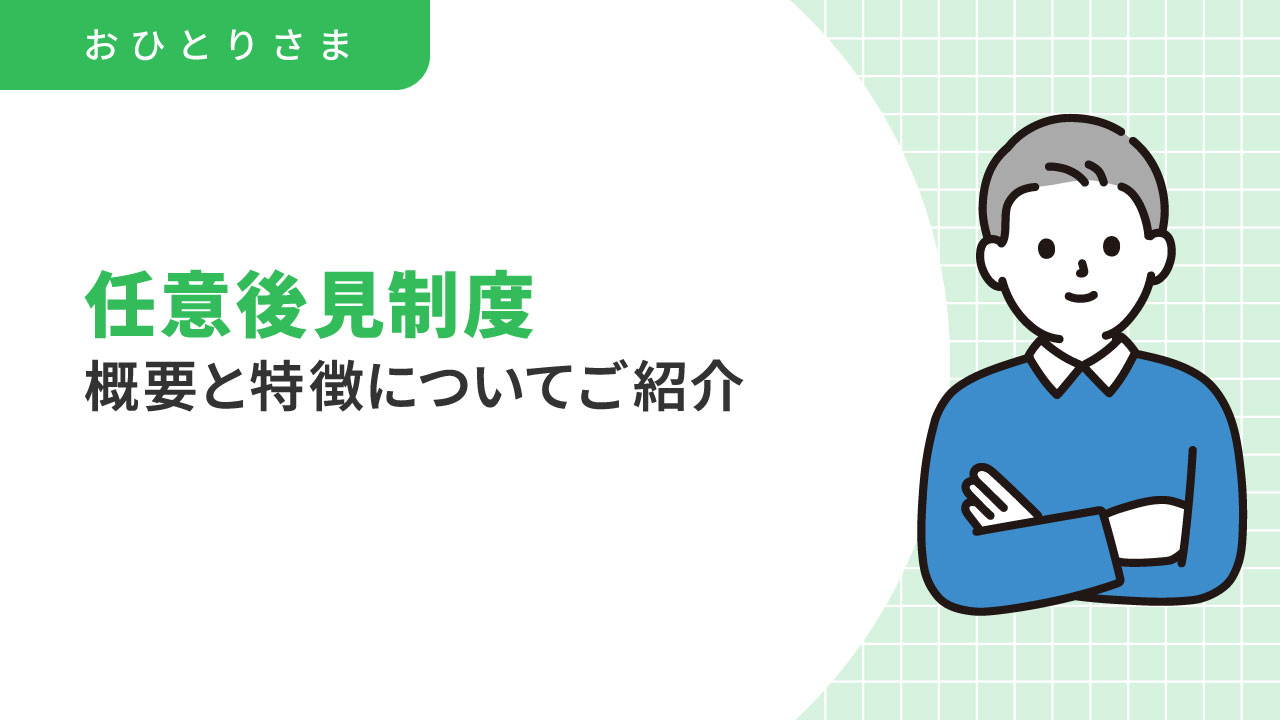認知症リスクを身近なものとして考えざるを得ない昨今、「成年後見制度の仕組みについて知りたい」という問い合わせが増えています。今回は、法定後見制度と任意後見制度の概要について、しく見ていきましょう。
成年後見制度の概要
成年後見制度とは、後見人等が判断能力の衰えた人を「財産管理」と「身上監護(介護、医療などに関するサービスを受ける上で必要な契約の締結等)」の両面でサポートする制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。
「法定後見制度」とは
法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた状態となった後、家庭裁判所に申立を行い、後見人等を選任してもらう制度です。これに対し、任意後見制度は、将来、判断能力が衰えた場合に必要な支援が受けられるよう、本人の判断能力があるうちに、信頼できる人との間にあらかじめ契約(任意後見契約)を結んでおくという制度です。任意後見契約は、必ず公正証書で締結する必要があり、公証人の嘱託により法務局で登記されます。
「任意後見制度」とは
任意後見契約の相手方(任意後見受任者)については、自由に選ぶことができます。法務省の調査では、任意後見受任者の内訳は、親族が約70%、専門職(弁護士、司法書士など)が約17%、知人等が約6%、その他団体が約6%となっています。また、任意後見人にどのような代理権を与え、どのような支援をお願いするかについても、契約で自由に決めることができます。任意後見人の報酬についても契約で自由に決めることができますが、親族が任意後見人となる場合、無報酬としているケースが一般的です。
任意後見契約締結後、本人の判断能力が衰えてきた場合、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行います(本人、配偶者、四親等以内の親族も申立を行うことが可能です)。任意後見監督人は、任意後見契約に基づいた支援が適切に行われるかどうかをチェックする役割を負っており、通常、弁護士、司法書士などの専門職が選任されます。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は任意後見人となって、本人のために契約に基づいた支援を開始します。なお、任意後見監督人に対しては、報酬の支払いが必要で、報酬額は家庭裁判所が決定します(本人の財産額に応じ、月額1~3万円程度)。
なお、任意後見契約を途中でやめたいと思った場合、任意後見監督人選任前であれば、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できます。任意後見監督人選任後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
まとめ
元気なうちに認知症対策を講じておきたいとお考えの方には、任意後見制度の活用という選択肢があります。法定後見制度と比べ、自由度が高く、本人の希望を反映した支援が受けられるとされている任意後見制度ですが、留意点もあります。元気なうちに認知症対策を講じておきたいとお考えの方は、シニアと家族の相談室までお気軽にご相談ください。