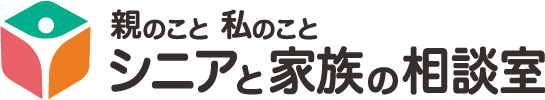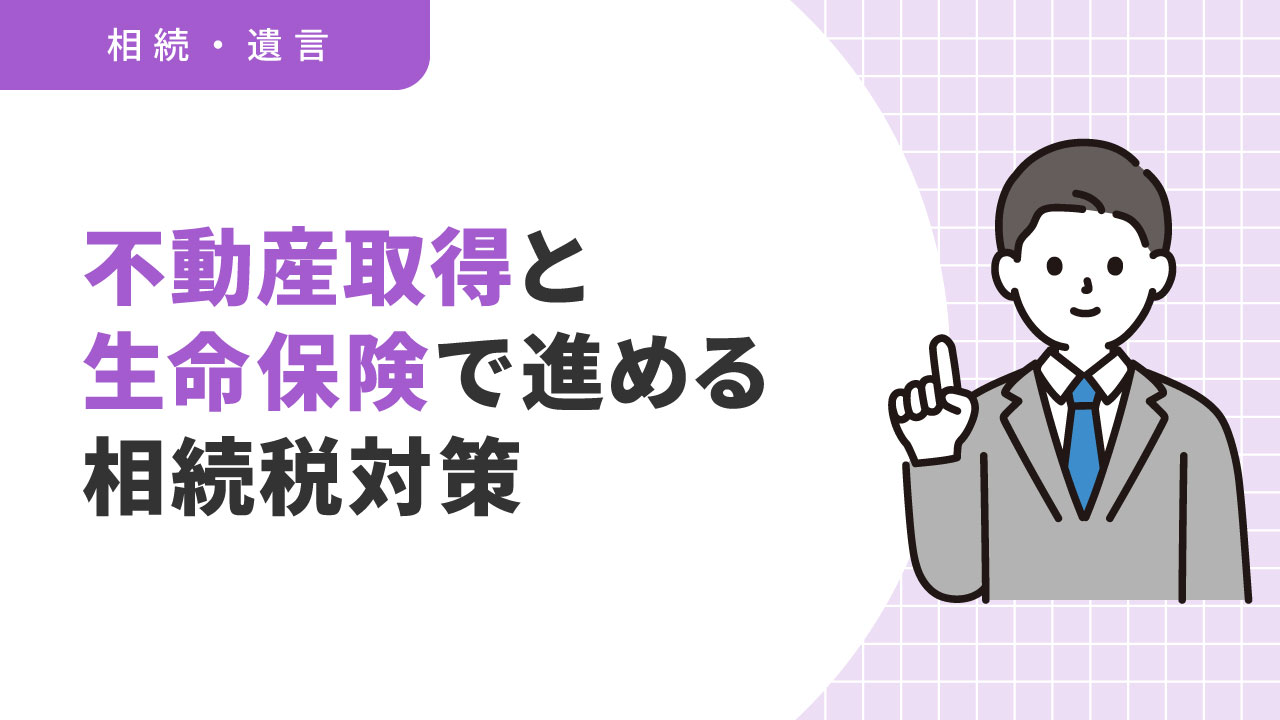相続税対策の手法としてよく使われるのは、「生前贈与」「不動産の取得」「生命保険の非課税枠の活用」の3つです。
今回は、「不動産の取得」について、ご説明したいと思います。
不動産の取得と相続税対策
Aさんが現金5,000万円を持っていて、それが全財産という場合、Aさんの財産の相続税評価額は5,000万円となります。
Aさんには、配偶者と子供1人がおり、法定相続人はこの2人です。相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は4,200万円。このまま、Aさんが何の対策も行わない場合、相続税が発生してしまいます。
ここでAさんが、現金で4,000万円のマンションを購入すると、Aさんの財産の内容は、「現金1,000万円と4,000万円で購入したマンション」に変化します。この場合、Aさんの財産の相続税評価額は、どうなるでしょうか?
現金の相続税評価額は1,000万円ですが、マンションの相続税評価額は4,000万円の70~80%程度の水準(2,800万円~3,200万円程度)になると思われます。
現金が不動産にカタチを変えることにより、相続税の評価額が引き下げられたのです。
現金をあわせた全財産の相続税評価額は、3,800万円~4,200万円程度となり、基礎控除の範囲内におさまる可能性が高くなります。
また、Aさんがこのマンションを賃貸した場合、マンションの相続税評価額は更に引き下げられ、4,000万円の50~60%程度(2,000~2,400万円程度)になると思われます。
あわせて遺言の作成もおすすめ
遺産分割を考えた場合、不動産は金融資産と比べて分割しづらいという特性があります。
分割しやすい金融資産から分割しづらい不動産に資産のカタチが変わることで、遺産分割が難しくなる可能性もあります。
そんな場合は、遺言の作成がおすすめです。「自宅は長男に、賃貸アパートは長女に、賃貸駐車場は次男に」というように、遺言で相続する人を決めておくことで、遺産分割におけるトラブルを未然に防ぐことができます。もちろん、その前提として、家族間でのコミュニケーションと合意形成が重要になることは言うまでもありません。
まとめ
不動産の相続税評価額は時価よりも低いため、不動産の取得は、相続税対策になります。一方、遺産分割においては、不動産は分割しづらいため、誰がその不動産を相続するか、家族間の合意形成を図りながら、遺言の作成などの対策を講じておくことがおすすめです。
シニアと家族の相談室は、税理士、司法書士、不動産の専門家、ファイナンシャルプランナーなどと幅広く提携していますので、相続についてのお悩みをワンストップでご相談いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。