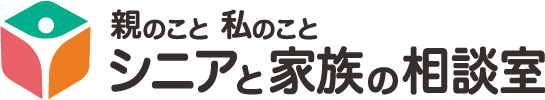遺言がなく、相続人が複数いる場合、相続手続きは、「相続人の確定(戸籍謄本の収集)」「相続財産の調査(財産目録の作成)」「遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)」「各種名義変更手続き(相続登記、預金の解約等)」というステップを踏んで進められます。
これらのステップの中で、今回は「相続財産の調査」のポイントについて、考えてみたいと思います。
被相続人の財産を把握するには?
被相続人の財産は、その種類ごとに、下記のように調査を進めていきます。
預貯金
預貯金の場合、通帳やキャッシュカードなどを手がかりに取引金融機関を特定し、相続発生日現在の残高証明書を取得します。
「亡くなったら、預貯金の口座が凍結する」という話をよく聞きますが、自動的に口座が凍結するわけではなく、相続財産の調査の過程での相続人とのやり取り等を通じて「金融機関が被相続人の死亡の事実を把握した時点で口座が凍結する」というのが正確なところです。
株式
上場株式や投資信託の場合、証券会社から定期的に送られてくる取引残高報告書等が手がかりになります。取引証券会社がわかったら、預貯金同様、相続発生日現在の残高証明書を取得します。
ネット証券の場合、取引残高報告書が郵送ではなくメールなどで届いている場合もありますので、被相続人のパソコンやスマホの調査が必要になる場合もあります。
不動産
不動産の場合は、市区町村から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書が手がかりとなります。また、固定資産税が課税されない不動産や、代表者のところに固定資産税の納税通知書が送付されており、被相続人には送付されていない共有不動産などの場合、権利証・登記識別情報・名寄帳の確認も必要となります。
相続財産の調査は、地道で大変な作業です。生前に相続人との間で財産についての情報を共有しておくことができれば、いざ相続が発生した場合の相続財産の調査が格段にスムーズに進むと思います。エンディングノートを活用するなど、生前の対策をおすすめします。
マイナスの財産が多い場合は相続放棄も視野に入れて
相続財産には「プラスの財産」だけでなく、借入などの「マイナスの財産」が存在する場合があります。
「マイナスの財産」が「プラスの財産」よりも明らかに多い場合には、相続放棄が有効です。相続放棄を行うためには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。
相続放棄には、留意点もあります。いったん相続放棄が認められると、その後で大きな「プラスの財産」が見つかった場合でも原則撤回することはできません。
また、相続放棄をした人は、「初めから相続人ではなかった」ものとみなされますので、本来は相続人ではなかった人が相続人となり、その人が「マイナスの財産」を背負ってしまう場合もあります。相続放棄の申述は、単独で行うことができますが、自分の相続放棄が認められることにより、影響を受けることになる人には、事前に連絡しておくことも必要です。
まとめ
相続財産の正確な把握は、その後、遺産分割や相続税申告を行う上で非常に重要です。
預貯金、株式、不動産など広範囲にわたる財産の調査は手間がかかるため、元気なうちにエンディングノートなどを活用して財産の内容を整理しておくと、ご家族の負担を大幅に軽減できます。
相続手続きや相続対策でお悩みの方は、シニアと家族の相談室まで、お気軽にご相談ください。