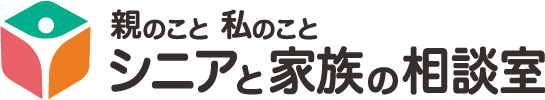遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行い、侵害された遺留分を取り戻すことができます。特定の相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効ではありませんが、予想される遺留分侵害額請求に対する備えが必要になります。
今回は、生命保険を活用した備えについて、見ていきたいと思います。
遺留分とは?
「遺留分」は、遺言によっても奪うことのできない最低限保障された遺産取得分で、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められています。基本的に「法定相続分の2分の1」で計算されますが、直系尊属のみが相続人となった場合は、例外的に「法定相続分の3分の1」となります。
遺留分を侵害する内容であっても、その遺言は無効というわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権」を行使し、侵害された遺留分を取り戻すことができます(遺留分侵害額請求権の行使については、期間の制限があり、相続の開始および遺留分の侵害のあったことを知ったときから1年間行使しない場合、時効により権利は消滅します。また、相続の開始から10年間が経過した場合、除斥期間により消滅します)。
このため、遺言の作成にあたっては、遺留分への配慮が必要となります。信託銀行の「遺言信託」では、遺留分を侵害する内容の遺言の作成は、原則、受付けてもらえません。
遺留分侵害額請求に生命保険で備える
しかし、財産の構成や家族間の問題など、さまざまな事情により、遺留分を侵害する内容の遺言の作成を希望される方もいます。
この場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性のある相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取る相続人以外の人)に遺留分侵害額を支払えるだけの資力があることが前提となります。
たとえば、「Aさんの相続人は長男と次男の2名、相続財産の総額は4,000万円」というケースで、「全財産を長男に相続させる」というAさんの遺言が残されていた場合、次男は遺言により遺留分を侵害されたことになります。
次男の遺留分は、法定相続分の2分の1の1,000万円です。次男は1,000万円の支払いを長男に請求することができます。長男が1,000万円を支払えない場合、トラブルに発展しかねません。
そこで、Aさんは生前に死亡保険金額1,000万円の生命保険(一時払い終身保険)に加入しておきます。Aさんの死後、死亡保険金1,000万円を受け取った長男は、これを原資として、次男から遺留分侵害額を請求されてもスムーズに支払いに応じることが可能です。
ちなみに、生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」に該当し、相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」で計算される相続税の非課税枠が設けられています。
法定相続人の数が2名のこの事例では、非課税枠は1,000万円。長男が受け取った死亡保険金は、非課税枠の範囲内です。Aさんが加入した生命保険は、長男の相続税対策にも役立ったことになります。
まとめ
遺留分侵害額請求に生命保険で備える手法につき、ご理解いただけたでしょうか?
シニアと家族の相談室は、遺言の作成、生命保険への加入など、ワンストップでご相談いただける相続・終活の総合相談窓口です。相続・終活のお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。